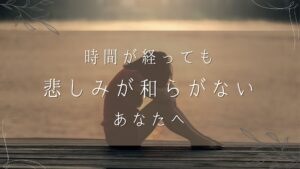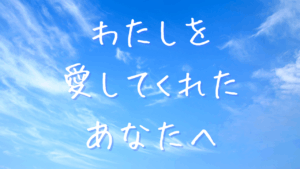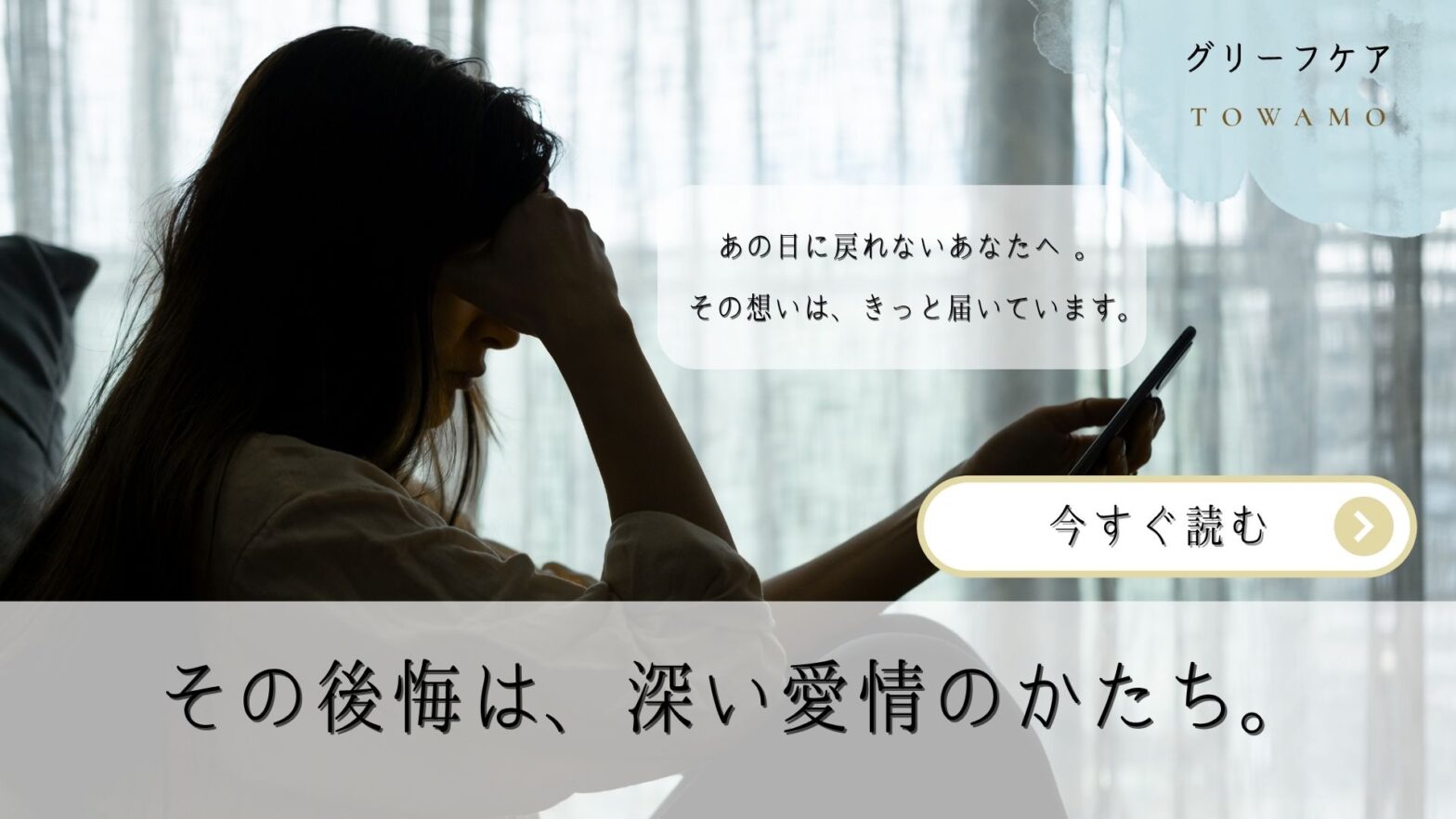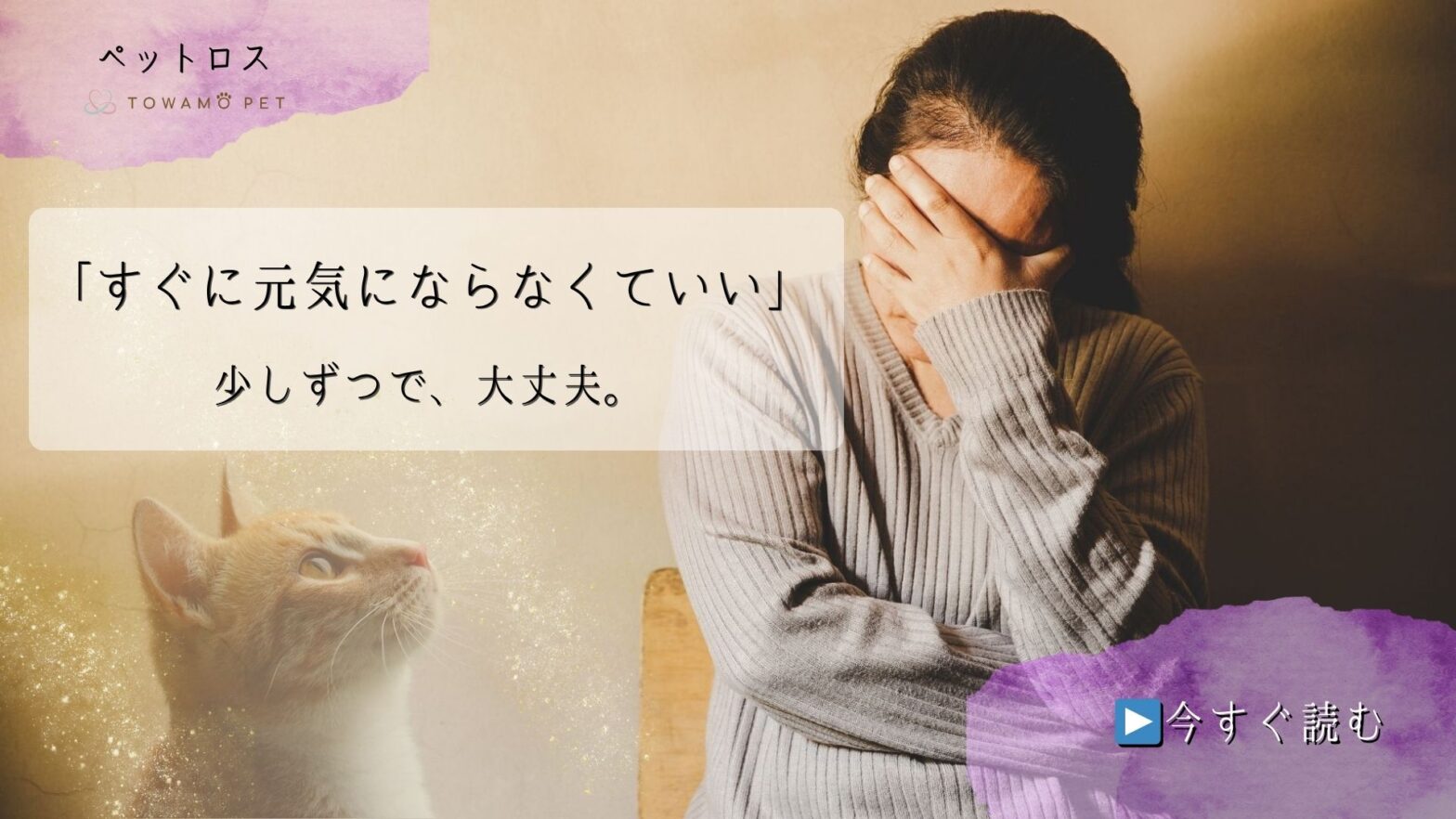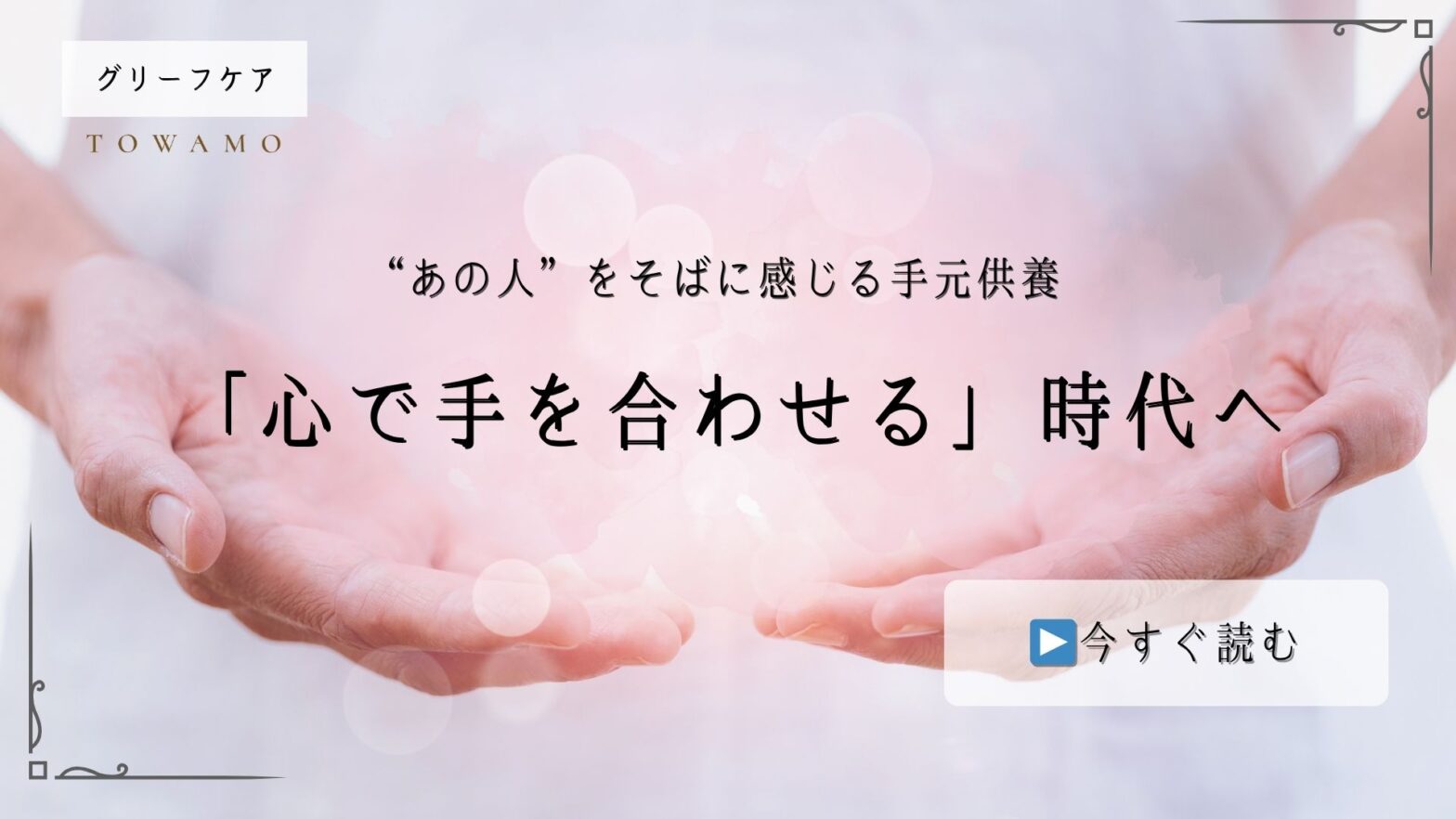大切な人との別れは、私たちに深い悲しみを与えます。
特に、長い月日を過ごしてきた家族であれば、その喪失感は計り知れません。
今回の記事は、8年間の介護を終えた女性の、喪失から再生への記録です。
深い喪失感に苦しみながらも、新たな自分を見つけていく姿は、同じ経験を持つ多くの人の心に響くでしょう。
グリーフケアの重要性と、人とのつながりが癒しをもたらす過程が丁寧に描かれています。
誰もが経験する別れと悲しみを乗り越える力を与えてくれます。
家族を看取った方々へのグリーフケアとしても、これから介護に向き合う方々の心の準備としても、支えとなる内容です。
母との静かな別れ

母が息を引き取ったとき、病室には静けさだけが満ちていた。
8年間、毎日続けてきた介護の終わりを告げる、あまりにも静かな瞬間。
最期の呼吸を見守った後、看護師が「お疲れさまでした」と声をかけてくれた言葉が、長かった時間の終わりを現実のものにした。
私は40歳。
母の認知症が進行し始めたのは32歳のときだった。
父は他界し、兄たちは遠方。
歳の離れた末っ子で、一人娘の私が、自然と母の主介護者になった。
最初は週末だけの手伝いだったものが、状態の悪化とともに日常へと変わっていった。
介護という日常

「お母さん、今日も良い天気ね」 朝の挨拶から始まる一日。
返事が返ってくることもあれば、私が誰なのか分からない日もあった。
認知症の進行とともに、母の中の記憶は少しずつ消えていった。
最初は昨日の出来事を忘れる程度だったが、やがて自分の娘である私の顔も分からなくなり、最後は自分が誰なのかも分からなくなった。
仕事と介護の両立は想像以上に難しかった。
リモートワークに切り替え、昼休みには母の食事介助。
夜中の徘徊で睡眠不足の日々が続いた。
友人との約束はキャンセルすることが増え、いつしか誘われること自体が減っていった。
「今夜、飲みに行かない?」
「ごめん、母のことがあるから…」
この会話を繰り返すうちに、私の世界は次第に狭くなっていった。
同年代の友人たちが結婚し、子どもを持ち、キャリアを築く一方で、私の時間は止まったように感じた。
恋愛も諦めた。
誰かを好きになる余裕すらなかった。
介護の日々は、喜びも確かにあった。
母が昔の歌を口ずさむ瞬間、私の名前を呼んでくれる日、「ありがとう」と言ってくれるとき。
そんな小さな宝物のような瞬間が、疲れ切った心を癒してくれた。
しかし、認知症は残酷だった。
母は次第に言葉を失い、最後の2年は寝たきりになった。
胃ろうを入れるかの決断を迫られたとき、私はどうすればいいのか分からなかった。
母の「延命はしないでほしい」という昔の言葉を思い出し、自然な形で最期を迎えられるよう選択した。
その決断が正しかったのかどうか、今でも時々考える。
突然の静けさ
母が亡くなった後の家は、信じられないほど静かだった。
8年間、常に誰かの気配があり、常に何かをしなければならなかった生活から、突然解放された。
この静けさが、私には耐えられないほど大きなことに感じられた。
葬儀が終わり、親戚たちも帰り、一人で母の部屋の片付けを始めた夜、私は初めて大声で泣いた。
介護中は「強くなければ」と自分に言い聞かせていた。
泣く暇もなかった。
でも母のセーターの匂いを嗅いだとき、堰を切ったように涙があふれた。
悲しみと同時に、心の奥には確かに解放感もあった。
それが罪悪感を生み、複雑な感情が渦を巻いた。
「もっとできることがあったのではないか」
「最期まで笑顔で看取れなかった自分は娘として失格だったのではないか」
自責の念が夜な夜な私を襲った。
友人は「よく頑張ったね」と言ってくれるが、その言葉が心に届かなかった。
私の中には「本当に頑張れたのか」という問いが常にあった。
介護の終わりは、8年間凍結していた自分の人生と向き合うことでもあった。
「これからどう生きるべきか」という問いに、答えを見つけられずにいた。
糸を紡ぐように

母の一周忌が近づいたある日、物置を整理していると、段ボール箱が見つかった。
中には母の編み物道具と、半分だけ編みかけのセーターが入っていた。
母は認知症になる前、編み物が得意だった。
私や父、親戚の子どもたち、みんなに何かしら編んでくれた。
私は箱から毛糸と編み棒を取り出し、手に持ってみた。
編み方なんて知らなかったが、なぜか「これを完成させたい」という気持ちが湧いてきた。
インターネットの動画で編み方を検索し、近所の手芸店で教室があることを知った。
勇気を出して参加してみると、そこには様々な年代の人がいた。
中には私と同じように親の介護を終えた後、趣味を見つけ直した女性もいた。
「介護が終わったとき、自分が何者なのか分からなくなるのよね」
その言葉に、私は思わず涙ぐんだ。
誰かに理解されたという安堵感だった。
編み物は思いのほか難しく、何度も解いては編み直した。
でも、糸が少しずつ形になっていく過程に、私は不思議な癒しを感じた。
あの介護の日々も、一日一日を積み重ねて作り上げた模様のようなものだったのかもしれない。
母の編みかけのセーターは完成できなかったが、私は自分のマフラーを編み上げることができた。
不格好だけれど、初めて自分で作り上げたものだった。
新しい日常を紡ぐ
編み物教室で知り合った友人との交流が、少しずつ私の世界を広げていった。
介護の経験を話せる場所があることが、どれほど心の支えになるか。
同じ経験をした人だからこそ分かる感情がある。
「介護うつ」という言葉があるが、私もまさにそうだった。
自分で気づかないまま、心と体が限界まで疲弊していた。
でも今は少しずつ、自分の感情と向き合えるようになってきた。
母への感情も複雑だ。
愛おしさ、感謝、時には怒り、そして今は深い喪失感。
でも母から学んだことは確かにある。
人生の最期まで見届けたからこそ知ることができた、命の重さと尊さ。
介護を終えて一年が経った今、私は少しずつ前を向いて歩き始めている。
編み物教室の仲間と小さな展示会を開いたり、介護経験者のオンラインコミュニティで体験を共有したり。
「介護後」の人生を少しずつ形作っている。
母の写真を見ると、まだ胸が締め付けられるような感覚がある。
でも以前のように涙があふれることは少なくなった。
時々、編み物をしていると、「お母さん、見てるかな」と思うことがある。
上手くできたとき、「まあ、上手ねぇ」と言ってくれそうな気がする。
介護と喪失を超えて

長い介護の後の喪失感は、想像以上に大きなものだった。
介護が私のアイデンティティになっていたからこそ、その喪失は自分自身の喪失でもあった。
でも少しずつ、介護者としてだけではない、新しい自分を見つけ始めている。
編み物を通じて、人と繋がることの大切さを再確認した。
糸が絡み合って一つの形を作るように、人と人との繋がりも、一つ一つの出会いや会話で紡がれていく。
母を介護していた頃は気づかなかったが、実は多くの人に支えられていた。今度は私が誰かの支えになりたいと思うようになった。
最近、地域の介護支援センターでボランティアを始めた。
介護の経験を活かして、今まさに介護の渦中にある人たちの話を聞き、時には具体的なアドバイスをすることもある。
「一人じゃないよ」 その言葉が、どれほど介護者の心を救うか。
私自身がそうだったから、その言葉の重みを知っている。
母の遺影に向かって「お母さん、今日はね…」と一日の出来事を話すことがある。
返事はないけれど、話しているうちに心が軽くなる。
母との関係は、形を変えて続いているのかもしれない。
介護の8年間は、私の人生の大きな部分を占めた。
苦しいことも多かったが、今は「あの時間があったからこそ、今の自分がある」と思える。
喪失の痛みは、新しい自分を見つける旅の始まりでもあった。
母が最期に私の手を握ってくれたとき、何かを伝えようとしていたように思う。
もしかしたら「ありがとう」だったかもしれないし、「もう大丈夫」だったかもしれない。
今なら、その握手に込められた想いを少しは理解できる気がする。
編み物をしながら、私は糸を紡ぐように新しい日常を紡いでいく。
悲しみを抱えながらも、一歩ずつ前に進む。
それが、母から教わった最後の、そして最も大切な教訓だったのかもしれない。
⚫︎あなたの心を癒すアイテム⚫︎
⚫︎あなたにおすすめの記事⚫︎
⚫︎あなたにおすすめの動画⚫︎
この記事を書いた人
⚫︎中村はな⚫︎
メモリアルアドバイザー兼ライター
大切な方との思い出を形に残すお手伝いを専門とし、これまで1,000件以上のメモリアルグッズのコーディネートを手がけてきました。
ご遺族の心に寄り添った記事執筆を心がけ、メモリアルに関する執筆実績は500件以上。
グリーフケアを専門としているため、お客様の心情に配慮しながら丁寧な説明と提案が可能です。
大切な方との思い出を末永く心に刻むお手伝いをさせていただきます。